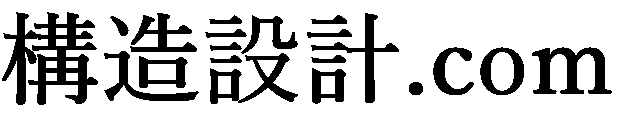液状化の可能性がある地盤の場合、液状化が生じても上部構造に影響が出ないように基礎形式を決定する必要があります。ここでは液状化が生じるメカニズム、液状化が生じやすい地盤、構造設計における液状化判定結果の取り扱いについて解説します。
液状化が発生するメカニズム
土(粘土・シルト・砂・礫)は土粒子と間隙(空気・水)で構成され、このうち砂は土粒子間で押し合う力(有効応力)が常に働いていることで固体としての強度(せん断強度)を保っています。ところが間隙部分に水が飽和している飽和砂質土では、地震によって大きく揺らされると間隙水圧が上昇する一方で有効応力が減少してやがて0となり、個体としての状態を失って液体のような性状を示します。これが液状化が発生するメカニズムです。
液状化すると、鉛直・水平方向に激しく流動するほか、間隙水が地表面に排水される際に噴水・噴砂がみられるなど、様々な現象が起こります。液状化が発生してしばらく経った後は排水された水量分だけ地盤沈下が生じます。
液状化が起こりやすい地盤条件
液状化が起こるための土の必要条件は
-間隙が大きい
-揺れが大きい
-間隙水圧が高い
です。
これらの条件を満たしやすい地盤は以下の条件をすべて満たす砂質地盤です。
-深さが20m以浅の沖積層
-砂質土で粒径が比較的均一な中砂
-地下水で飽和している
-N値がおおむね15以下
反対に、どれかひとつでも当てはまらないような地盤では地震時に液状化が生じる可能性は低いと言えます。
地震の大きさ(加速度・マグニチュード)は液状化のしやすさに直接影響します。
一旦液状化が生じた地盤では、再び液状化が生じる可能性が高いということにも注意する必要があります。
液状化するかしないかはどのように調べるのか
建設地において、
-地下水位の測定
-N値を調べる標準貫入試験を行う
-細粒分含有率を調べるための粒度試験を行う
ことが必要となります。
敷地の建築面積が小さい場合はこれらの試験は1箇所で十分ですが、建築面積が大きい場合は2箇所以上行う必要があります。
なお地形などにより液状化発生の可能性が極めて低いと判断できる場合は、このような試験調査による液状化判定は省略されることもあります。
例えば洪積層である関東ローム層に該当する地盤、山地、丘陵地、台地であれば地震時に液状化が生じる可能性は非常に低いと言えます。
また以下のサイトでは東京都に限り地域別の液状化予測図が公開されています。
(https://doboku.metro.tokyo.lg.jp/start/03-jyouhou/ekijyouka/top.aspx|東京の液状化予測図 令和3年度改訂版)
東京都以外でも、行政によっては液状化予測図が公開されているところもあるので、建設地の対象となる行政のHPを調べて確認しておくことが望ましいと言えます。
FL法による液状化判定
FL法は調査ボーリングで得られる N値と粒度試験の結果を用いて液状化の危険度判定を行う方法で、簡便でありながら所定の深度についての危険度予測ができるため液状化判定において一般的に用いられています。算定の結果、FL≦1であれば液状化の可能性があり、FL>1であれば可能性が小さいという判断となります。
h2 構造設計における液状化判定結果の取り扱いについて
FL値で検討する場合、150galでFLが1以上であれば、一次設計時において地盤や杭の検討において液状化の恐れがないとして取り扱います。二次設計で液状化をどのように考慮するかは、設計者判断によります。ただし沈下の影響を受けやすい構造形式で、上部構造の性能設計を行うような場合は、検討しておくべきと考えられます。また、二次設計で液状化を考慮しない設計を行う場合は、一次設計における液状化の検討に用いる加速度レベルを200galとすることが推奨されます。
液状化発生の可能性があると判定された場合、液状化が発生しない深さまで杭又は地盤改良を行う必要があります。
それに加えて地震時における杭体・地盤改良体の応力検討において、水平地盤反力係数を低減する必要があります。
まとめ
液状化が生じるメカニズム、液状化が生じやすい地盤、構造設計における液状化判定結果の取り扱いについて解説してきました。基礎形式・地盤補強の有無を決定するにあたり、液状化判定結果を含む地盤調査結果から適切な判断をすることが必要です。